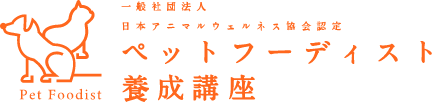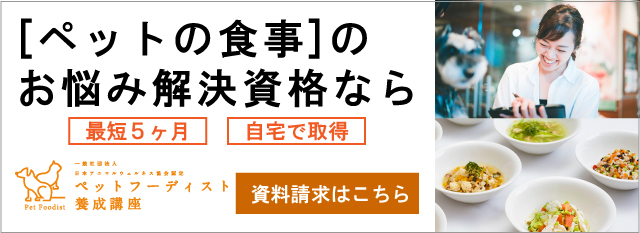ペットの食事と仕事 豆知識

ペットフーディストの資格取得を検討中の方からよくいただく質問の1つに「病気に対応できる食事の知識はつきますか?」というものがあります。
当講座では、犬猫の病気用の食事として利用される【市販の療法食】について学べます。「療法食じゃなくて、手作り食で病気に対応する知識がほしい」という質問もたくさんいただきますが、まず、
■各病気に対し、食事では何ができるの?
■それをふまえて、療法食は普通の食事と何が違うの?
を知っていただく必要があります。当講座で学べる療法食の知識を、一部ご紹介します。
『病気に食事で対応する』とはどういうこと?
病気がある場合、動物病院にいくと
◎外科治療 ◎投薬 ◎生活習慣の見直し ◎リハビリ
など、さまざまな「治療」を行います。そんな中、食事では何ができるのでしょうか。
食事は、体が栄養素とエネルギーを利用するために摂取します。
栄養素とエネルギーを体内で利用できる形にするために、体はさまざまな「代謝」(体内での化学変化・エネルギー変換)を行っています。病気になると、この代謝に何らかの変化が起きます。
病気のときの食事管理は、たとえば
■その代謝の変化を正常化させる
■これ以上負担をかけないようにする
■再発の防止や予防
これらのいずれか、もしくは複数を目的として行います。
病気に対して食事でできることとはこういったことであり、これを「食事療法」と呼びます。また、各病態に対応した特別な食事は【療法食】といいます。
ペットフーディスト講座では「療法食」の何を学ぶ?
当講座では、犬と猫によくみられる病気別にこんなことを学びます。
1.病気と食事療法のあらまし
・各病気でどんな異常が発生するか
・その異常が起こると、どんな症状が出るか
・食事療法としては何ができるか
<当講座で取り扱う病気>
◎肝臓 ◎腎臓 ◎尿路 ◎内分泌、代謝 ◎心臓
◎食物アレルギー/食物不耐症 ◎がん ◎骨・関節 ◎肥満
2.市販の療法食の詳細
上記をふまえて、こちらも学びます。
◎市販の各病気の療法食では、成分・製法的にどんな調整がされているか
◎療法食で食事療法を行うために与え方(頻度、回数、タイミング、一工夫など)はどうしたらいいか
ペットフーディスト養成講座なら、犬と猫の【食事の知識】+【仕事に使える実践力】が身につきます。